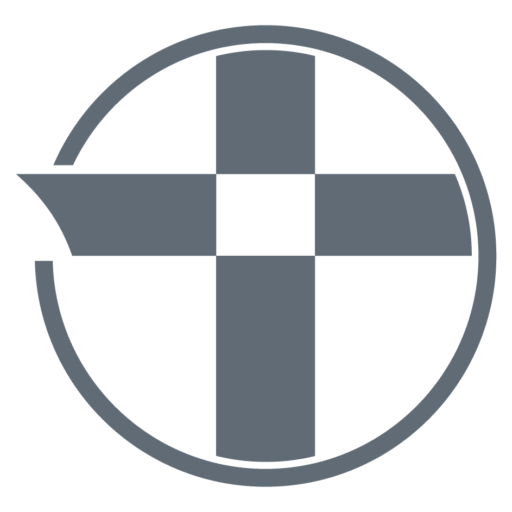新海誠作品において、個人的な一番大切な趣向でいうと、キャラボイス(CV)のミスキャスティングという視点は切り離せないわけですが、ここでは世界観の創出という部分にだけに絞らせていただきたいと思います。
どう記しても古参ぶった嫌らしい書き方になりそうなので先に書いてしまうと、「BITTERSWEET FOOLS」( 2001年8月 minori) 、「Wind -a breath of heart-」(2002年4月 minori) 「ef」(2006年12月 minori) など、これらの新海監督の作品であるオープニングムービーを重ねていく中で、この世界をもっと見たいと思うようになりました。

これら美少女ゲームについては、監督が指揮をとった映画作品に負けないくらい個人的に思い入れが大きく、他の作品も語り始めると止まらないわけですが、今作の「君の名は。」(2016年8月) の他に、普通に視聴することができる「秒速5センチメートル」(2007年3月) をメインで織り交ぜながら思いを語りたいと思います。
描写の細かさとは愛である
美術関係でデッサンをしばらく続けていたかた、とりわけ1つの物(オブジェクト)に長時間かけて描写を試みたことがある人なら、新海作品の背景描写の細やかさは「異常」ではないことがわかるかもしれません。
かつてここまで写実的に描写する人がアニメでは少なかったことが、細やかさの印象を強めているように感じます。技法としては純粋なデッサンが基となっていて、そこに一部イメージとして意図的な強調(特に光や焦点・ライティング)などの合成やボケが施されています。

いままで写実的なアニメが少なかった理由は明快です。実写のような表現をアニメでやる必要性を考えられなかった。浮世絵もそうだとおもいますが、商業ベースのアニメは記号化や簡略化が求められ、それこそが商売をするうえでコストパフォーマンスです。頭を使って作る工程を簡略化して制作時間を短縮し、一方で見る方も見やすく想像力が掻き立てられる。そういった考えが当然のように存在していたように思います。
趣味であっても個人で細かな描写をやろうと思うと、すべてアナログでは時間が足りず、デジタルでもかつてはコンピューターの処理能力が足りませんでした。そのスペックが向上してきたタイミングと、鉄腕アトム以降にアニメの記号化が定着しきった中で、この「アニメ業界」にこのタイミングで生まれてきた異端さが、「君の名は。」の大ヒットの引き金となっていたように思います。
新海監督の表現は、平面構成を作るよりも「創る」部分で頭は使わないものであるはずです。しかし一方で、描き上がった複雑な背景の上に、細かい部分での描写の根気や、光のライティングなどの気配りを加えたり削いだりする箇所は、観察力や経験と、非常に神経が使われるものだと思います。
さらに心を揺さぶられる別の要素があります。それは描写の細やかさではなく、切り取る部分と大きさの選択、いわゆる構図です。これを初めて教えてくれたのが「Wind -a breath of heart-」(2002年4月 minori) オープニングです。ここで衝撃を受けつつも、当時はむしろニヤついてしまったのが、例えばクルクルパーが全画面で描写されていた時の事。
クルクルパーとは鉄道が好きな方ならなんとなく聞いたことがあるかと思いますが、特殊信号発光機のことで、ホーム上の非常停止ボタンを押したり踏切内に人や車が立ち入っているとき、運転士へ危険を知らせるための信号です。例えば一般の人が触れる踏切のランプが点滅しているシーンであれば情景としてわかるのですが、これをあえて選んでいるのが象徴的です。特殊信号発光機は、そこに出すことの意味の強さより、風景の一部で普段なんとなく目の中にそっと入ってきているものを表しているのだろうと感じました。

ただ細やかな部分に視点が行っていることだけではなく、それは暗に、監督が「あなたが普段見ているものを私たちもみていますよ。」という安心感も与えてくれます。実写映画でも似たような技法はありますが、どちらかというと細かなパーツにピントが合っているときは、そこに心情描写や意味や軽い伏線があることが多いように感じます。これは従来のアニメの記号化・簡略化された表現では伝わりづらく、まさに実写的な表現の副産物かもしれません(それがしたくて拘られているのかもしれません)。
情報の質だけでなく、それを選んだ構図までもが私生活を感じさせてくれるわけです。
当たり前の中にある異質なもの
2007年に公開された「秒速5センチメートル」では、「時間」と「距離」が描かれています。公開当時から10年前の中学生時代、そして公開当時の大人となった登場人物の時代。東京と種子島、東京と岩舟(栃木)など。その距離感と時間の経過が、この作品のタイトルの桜の花びらが落ちる時のスピードに表されています。

この作品はキャラクター描写について焦点が当てられることは少ないように感じます。それもそのはずで、際立つ背景とは対照的に、キャラクターへの描写は強くありません。もちろん描写は背景同様に徹底されるほどに好ましいのかもしれないけれど、作品性という意味で、これは象徴的な部分だと思います。
時間経過と距離って空間の中に自然と存在していて、人間のいう空間というのは、自分以外の全てを表すものだと思います。日本的な言い方だと茶室がそういったものになるかもしれません。そこで他の全ての作品と同じようにこの作品も人間を描写するわけですが、それを人間以外の部分から攻めていくところに、注力されていたのではないかと考えています。
解釈次第では失礼かもしれませんが、この作品においては驚くほど「表情」に印象が残りません。また声も強い印象は残りません。それについては、コメンタリー映像で監督自身が等身大の人物を起用したいということで、例えばヒロインに年齢が近い新人を起用したとのことで、あえて強い印象を与えないようにしている面も感じました。

むしろ印象に大きいのは、向かってくる電車のライト、暗い田舎道、温かさを感じるストーブ、積雪で運転を見合わせて息詰まる車内、そんな一つ一つの空間です。それらはただ空間をわかりやすく伝えるだけでなく、ホームの柱、足元の雪の感触、自販機の蛍光灯、そう言った実写映画にあるような細かい描写シーンを部分的に強調し、その描写が空間とともに印象付けられます。
人物の心象を主軸とした話ながら、映るパーツは当たり前のものばかりで、その組み合わせによって人物像が引き立っています。
この作品が知れ渡ったのも、まだ 2ちゃんねる が日本のインターネット上で幅を利かせていて、ソーシャルネットワークサイトもコミュニケーションアプリもはっきりとは出てきていない、当時でもちょっと便利とは思えなかった2005年前後の情報伝達の中で、自然とインドア派な、親しい人の顔すらじっとは直視できない私のような人間には心に響いたものです。
発表された時代背景もメディアがオタクというものへの理解が薄く、恰好のいち消費素材としてのみ存在していて、オタクという単語が取り上げられるたびに悪い意味でしか使われていないような時代でした。しかしながら、今(発表時)とその10年前を比較するという作品の懐古的な性質がオタクの心をくすぐりながら、劇中にはこれといったオタクっぽいものがない。それが新海監督にとっても、また当時のオタクにとっても、何か精神的な部分でのきっかけとなったような気がします。
(ちょっと、この続きを含めて当時が悪いような印象を持たれてしまうかもしれないので、メモをしておくと。当時は確かに現実社会では風当たりが強く、とてもオタクだなんで言えませんでしたが、一方でオタク同士では同族意識があったせいか、非常に牧歌的な時代でした。だからこそ、例えばネットと現実は切り離されていたものでした。)

それからまたさらに10年が経とうとした今。メディアの形も変化してきていて、何よりも当時オタクとして半ば虐げられていたものが、若い世代では普通に自分たちの一部として存在するようになりました(そういう意味で、2016年版の秒速5センチメートルがあっても面白いなと思います)。
名前という彩りを添えると
その後、新海さんご自身が色々と経験を重ねられてきたことはブログなどで拝見してきました。
そして2016年公開の「君の名は。」発表された予告映像を見て、つい笑みがこぼれてしまいました。
まさに、美術的によく言われるブラッシュアップというやつで、新海監督の世界そのままに、ポップで馴染みやすさがあって、懐かしさと心を揺さぶる感じ。でもそれに加えて強いキャラクター性。さらに日本的な雰囲気。それが予告映像だけで伝わってきました。
インタビュー にもあるように、今作では今までの切なさや涙だけでは無い「笑わせる」に挑戦されていたようです。いままでは「観客と入れ替わる」所に重点が置かれ、みずからキャラクターの顔はなくてもよしとしていたと仰っています。
今作でキャラクターからの笑いに挑戦した結果、そのキャラクターの個性を鮮明にせざるを得なくなり、結果的にその挑戦が監督本人の狙い道理に喜怒哀楽のすべてに行き渡ってバランスが取れた作品になっています。

元々個人的な印象としては、会社勤めから独立して映画をほぼ一人で作り上げちゃうように、根底にある意思はすごく強いのだけれど、表層的には(失礼ですが)なよなよとした印象であり、そのはかなさもこそ魅力でした。
しかし今作は自ら代表作になる物だと仰っているとおり、発表の時にちょっとだけ誇らしげだった表情が印象的でした。
永遠 : 存在
さて話は変わり、冒頭の美少女ゲームの延長になります。
秒速5センチメートルが公開された年、全く別に Little witch というメーカーからピリオド(2007年12月発売) が公開されました。

ここでは作品自体よりも、テーマソングを歌うのはpigstarというアーティストの曲について、当時から新海誠監督の描く距離感というか宇宙の大きさが似ていると思っていました。
ピリオドの主題歌、pigstar「永遠の存在者」では、冒頭は以下の歌詞で始まります。
永遠の存在者が この世界にいたとして
一度きりの命なんて 嘲笑うに違うない
これはセカイを見つめる視点であり、秒速五センチメートルでも視点としては叶わない世界・宇宙・時間・距離に争う主人公とヒロインが描かれています。

一方で、今回「君の名は。」で起用されたRADWIMPS・主題歌「スパークル」では冒頭で
まだこの世界は
僕を飼いならしていたいみたいだ
と敵わない存在への抗いのようなものを描いています。しかしそんな当たり前だとか抗えないものに続けて、少し能動的な一面を見せます。
運命だとか未来とかって言葉が
どれだけ手を伸ばそうと
届かない場所で僕ら恋をする
これは同アーティストの「君の名は。」作中歌「前前前世」でも見られます。
心が身体を追い越してきたんだよ
といった文言があります。
しかし同時に下記のように続きます。
もう迷わない また1から探し始めるさ
むしろ0から また宇宙を始めてみようか
まっすぐで力強さを感じます。ロックならでは。能動的で、しかも世界を包括してしまう言葉があります。
これらは二つの全く違うアーティストが奏でれば当然差が出るわけですが、なんとなく新海監督の深層心理とその変化には近いような気がしてしまいます。特にRADWIMPSは監督自らが起用したと話しており、自らの変化の象徴とも取れます。

また台詞でいうと「秒速五センチメートル」のトレーラーの冒頭はヒロインの言葉から始まります。
あの人との約束の当日は
昼過ぎから雪になった
呼応するように主人公も続きます。
僕たちの人生には
巨大すぎる人生が
茫漠とした時間が
どうしようもなく
横たわっていた。
このような強い言葉を置いていきます。
主人公の抗えない世界への恐怖と、立ち向かうべきものからの逃避と、その逃避への陶酔と、自分がメインとなったその絶望すべてが愛おしい部分を描写していす。
彼の心がどこにあるのか
わかった気がした
ヒロインも一番意思を感じる言葉でもこういった不確定な部分にとどめていました。一見悟りのようなさらっとした言葉。これがこの作品では一番強いと思われる「意思」です。
それが「君の名は。」では、自分たちの意思で、二人がそれぞれの方法によって時間軸を越えていきます。
視覚をメインとしている話の流れから言うとずれてしまうので、詳しくは書きませんが、今回の「君の名は。」は、むしろ「音」。音楽とムービーとの調和が、一番光っている部分なのではないかと思います。ここでは視覚的な要素だけを切り取って語らせて頂いていますが、むしろ今作において監督自身が注力し、また影響を与えられたのは音なのでは無いかと思いました。
新海監督自身、オタクであるということを特に隠してはいませんが、今後あえて自ら公に過去を語ることはないでしょう。でも自身の遺伝子をしっかりと認識し、作品に反映しているので私は寂しくありません(少しだけの強がりはお許しを)。
さらには、取り上げた場面、背景、素材、表情たちが一般受けするどころか、誇らし語れるようになった「このセカイ」に感謝しないといけません。そして思い違いの部分はあるかもしれませんが、過去作品に出てきた登場人物を配置したり、実際にある文化を盾にして口噛み酒と「それを売ったら?」という流れを持ち出したり、さらっとスカートから見える下着が映ったり、また男の子が女の子の胸を揉むことを(男女の心が入れ替わったというのを逆手にとって)間接的にやってのけたり、ジブリでは嫌らしくもあえて避けてきた表現が散りばめられていたことは、その監督のバックグラウンドを表しているようで嬉しかったです。
監督の人間性
秒速5センチのコメンタリーで「主人公のような恋愛をしたのか」という質問に対し、ほんの少しだけ照れたように「経験したことはないです」と否定されていました。

でもインタビューアーにその質問をさせるように、監督の作品の主人公は監督と重ねる部分があるように見えます。
今回の作品の番宣で、ある番組で主人公の声優、神木隆之介さんと一緒に出演された際に、彼を「かわいい」と言っていました。作中のキャラクターと重ね合わせていることは確かだと思いますし、彼ありきの部分もあったと自身で言っておられましたが、思い入れがそう言わせるまでになった部分があると思います。
新海さん自身が作品を創る過程を経て、その作品によって自分自身に影響を与えているのだと思います。回を重ねるごとに(時に失敗というのもあるだろうけど)、より良い作品になっていく、そして過去の作品も細部までよく見えるようになっていく。
すべてのものを割れ物を扱うように撫でるように丁寧に作り扱う。
その力が新海誠さんという人の魅力だと思います。
『君の名は。』、誰かと約束して観にいったり、思い切ってデートに誘う口実にしたり、1人で行って知らない誰かの隣に座ったり、観終わった後は映画の感想や愚痴を言いあったり、本作がささやかでも皆さんの生活の彩りのひとつになれば嬉しいです。せめてチケット代のモトは取っていただけますように。
— 新海誠 (@shinkaimakoto) 2016年8月25日
秒速5センチメートルでは製作中に、スタッフの中で結婚された方がたくさんいたと仰っていました。インタビュー中に「(秒速5センチメートルという)作品を制作する中でも、それぞれのスタッフがそれぞれの時間軸で生きていることへの証」として語られていました。これは、日本のクリエイティブな制作現場の環境というといいイメージはありませんが、意識的か無意識的かはさておき、それだけ安定していたムードや環境づくりを監督がされていた証拠でもあり、うらやましく、惚れ込む部分です。
私にとって、彼は「ただ(すごい作品を作れる)すごい人」ではない。
何より人として魅力が強い人です。
色男理論
私が専門学校にいきはじめてしばらくして、映像の課題がありました。そのとき、自分の中であるアイデアが浮かびました。
実写映像と2次元を混ぜる映像です。
具体的には、主人公を ●(黄い丸) で、それ以外の人を 〇 (白い丸)で表しました。影響しあう人物を記号で、そのシーンの合間を実写映像でつなぐという、奇妙な発想です。
案の定、企画書を提出したところ、ある中年の講師から怒られてしまいます。
「二次元と三次元が同一作品上で重ねることは許されない。絶対に!」
でも血気盛んだった当時、私は引き下がりませんでした。それが合法である限り、タブーに逆らって伝えてみたいという思いがあったからです。
そうして迎えた中間報告。大方の先生が見直すよう指摘する中で、ある先生が繰り返し言ってくるのです。
「君は色男だ。」
以後、その先生は私に直接的にも、恥ずかしいことにみんなの前でも繰り返し伝えてきました。それが当時は自分ではよく分からなかった。そして多分周囲の講師もその先生が私を気にかけるのかいまいち分からなかっただろうと思います。
でも今なら少しわかります。その先をちゃんと詰め切って研究を重ね、1コマの絵にも愛着があって、撫でるように描き自分の色を使える。その先生は知らなかったはずですが、わかりやすく言えば新海誠監督のような人なのだと思います。もっとも私の作業は比べるにも忍びないような、とても効果的なものではありませんでしたが、自分が作るものの対して自分が触れていて気持ちが良いものになるまで繰り返し描き続けるということ。
こういう人を色男と言う。
確かに「僕」は予備校でそう習いました。
それが監督への憧れの始まりであり、変わらない色男の今の姿です。いつしか精神的な面では監督を目指していたわけです。
誰しもが強い言葉、かっこいい言葉でまとめあげようとする芸術家やデザイナーなどの発言。テレビでは「チョイ悪親父」や「毒舌」が流行った時代でもありました。そんな中で秒速5センチメートルのコメンタリー映像で、優しく語られていた「生活の中にふっと溶け込めるような作品にしたかった」という表現は当時自分にとって衝撃的なもので、他のどんな強い言葉よりも、心に溶け込みました。

こういう考えだっていいんだ。独立して頑張っている人がいるんだ。それが何よりの安定剤となりました。
美術系というと、他の分野からどう思われているかはわかりませんが、確実にどこか「体育会系的な部分」もありました。じっさい、発想力や気力だけでなく体力勝負な場面も多いのです。だから新海監督の風貌とその新しい発言を受けて、それら以前からあったという考えを自分の中では「古臭い」と仮定して、自分の勢いにしてきました。今覚えば褒められたものではありませんが。
そして今回はその部分を裏切られたような気持ちと、また新たな意識を与えてくれた気持ちが心地よく混同しています。
監督は常に新しい意識を与えてくれました。直接ファンメッセージを送る方が適切でしょうが、この広い世界、どこかで誰かから伝わるかもしれない、その儚さと祈りに任せて一生直接は見られないであろうここに強い気持ちを置いておきます。
心をえぐりながらも治癒してくれ、日本の創作・世界の環境・社会・精神を受け入れ、変わらないものを変えながらも、覆す変化を常に与えようとしてくれます。