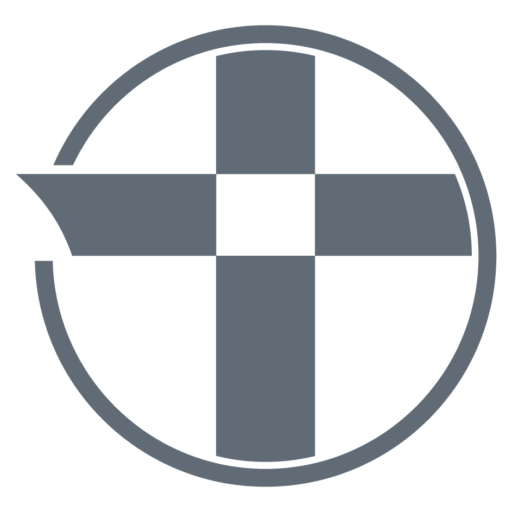東京・奥多摩と日原鍾乳洞のある東日原をむすぶバスでの運転手さんと車しょうさんの話し声をとった映像です。
東京の方言って言っても、なかなか標じゅん語とごっちゃになってわかりにくくなっちゃってるけど、その中でも「たまの言葉」(たま弁)をちょっと話してるバスの車掌さんと運転手さんの会話です。なまりはかなり少ないから、聞き取りやすいと思うよ。かわっているのは、単語よりも「のめっこい(なめらかな)」感じのノリだと思う。
失敗したり行きづまったりしたときに、「しょうがねーなぁ」ってあきらめる感じから、笑いにするのが変わってるんだよね。ちょっと考えられないかもしれないけど、たま地区は、同じ東京でも、けんかっ早い「えど」の下町の方とはちょっとちがった感じがある。
今の多摩地区を見るとわかりにくいかもしれませんが、ごもんそ事件などのいろいろな大変さが、“あきらめ”からの笑いや自分を茶化す気持ちを育てたみたいです。私のCOTAは、おじいちゃんとの話の中でそれを感じています。富士山の火山灰のせいか、お米を作れる農家はかなりしんどい方で、米を作れる農家でも、子どもたちだけにお米をあげて、学校を卒業したあとは麦ごはんしか食べられなかったそうです。
バスが走る日原街道は、狭くててごわい道路もあります。そこでは車と車がすれちがうのがむずかしい場所もたくさんあります。そこで、誘導をしてくれる人をおいて、バスが通るときにはトランシーバーで話しながら車をとめて通すということをしています。この動画は、その様子を写しています。うまくいかないとどうなるかも、この動画の始まりのところで見ることができます。
今のこの道路さえ、ちゃんとしたものだけど、何度も崩れたりして、何度も直しながらきた道なんです。その険しさは、まるでチベットみたいだといってもいいくらいです。そのたびにし直されている道は、今の旧旧旧旧旧旧道(第6期のバス放送で使われているトンネルができる前の道)も見つかっているそうです。日原の住民さんたちは、学校に通ったり、買い物に行ったりするのも、とても大変な道を毎日通っていたと想像できます。
そう考えると、このせまい道を走るバスでも、ずいぶんよくなったんじゃないかってわかるよね